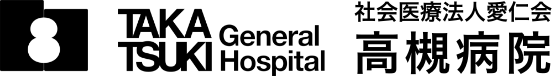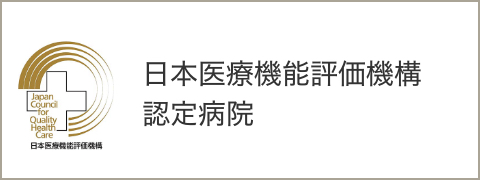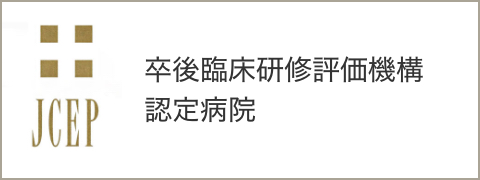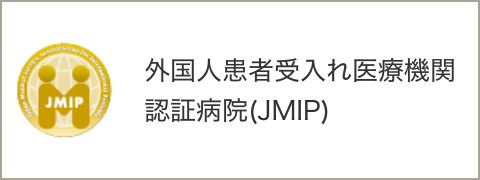循環器内科
診療科紹介

循環器内科について
循環器内科では、狭心症、心筋梗塞、先天性心疾患や弁膜症、心筋症、不整脈などの心臓の病気、大動脈や下肢動脈、肺動脈などの血管の病気、さらには高血圧や脂質異常症など生活習慣に関わる疾病の診療など広い範囲の疾患を取り扱っています。当科スタッフは休日・夜間も院内に常駐しており、24時間体制で循環器疾患の救急診療に対応できる体制を取っています。また、急性心筋梗塞や不安定狭心症(急性冠症候群)に対しては緊急でカテーテル治療ができるように心臓カテーテルチームがオンコール体制を取っています。適切で最良な医療を提供し、患者さんのみならずご家族の方々からも信頼される医療の実践を目指しています。
ごあいさつ
狭心症と心筋梗塞は"虚血性心疾患"と呼ばれ代表的な循環器疾患です。最終的な診断は、心臓カテーテル検査で行いますが、運動負荷心電図検査、心臓超音波検査、心臓CT検査や心臓MRI検査などを病態に応じて実施し、正確な診断と適切な治療を行っています。心臓カテーテル検査では、腎機能障害や高齢の患者さんに対しては、できる限り負担が少なるよう工夫して行っています。治療は、心臓カテーテル治療(経皮的冠動脈形成術)や冠動脈バイパス術のほか、薬物療法、食事療法や運動療法など積極的な生活指導による包括的治療が行われます。冠動脈バイパス術の適応がある場合には、当院の心臓血管外科と緊密に連携して迅速な対応を取っています。
虚血性心疾患に対する心臓カテーテル検査以外にも、原因不明の心筋障害を認める患者さんに対する心筋生検や、心不全、肺高血圧症の患者さんに対する右心カテーテル検査なども実施しています。
近年、喫煙習慣や生活習慣の欧米化に伴い末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)が日本においても増加していますが、当科では積極的にカテーテル治療を実施しています。カテーテル治療により、長時間歩けない、安静でも痺れ・痛みがある、などの自覚症状がある患者さんの生活の質が改善します。
心不全には、薬物療法だけでなく、当院不整脈内科、心臓血管外科と緊密に連携し、心臓再同期療法 [CRT](両室ペーシング治療)、外科的治療(心臓弁置換、心臓弁形成)など多角的に改善策を検討しています。特に重症な場合はICUで呼吸・循環の集中管理を行い治療します。また、早期の在宅復帰に向けて医師だけでなく、看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、管理栄養士、ソーシャルワーカーなどの多職種が多面的に介入しサポートします。
診療内容
- 経皮的冠動脈形成術(PCI)
- 末梢動脈疾患のカテーテル治療(EVT)
- 血栓溶解療法、下大静脈フィルター留置
- 経皮的心肺補助(PCPS)、大動脈内バルーンパンピング(IABP)、補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)
- 心筋生検
- 心嚢穿刺
- 心臓カテーテル検査(冠動脈造影検査、冠血流予備量比測定、右心カテーテル検査)
- 冠動脈CT
- 心臓MRI
- 経胸壁心エコー検査、経食道心エコー検査
- 頸動脈エコー検査、下肢動/静脈エコー検査
- 血管機能検査(ABI/PWV)
- トレッドミル負荷心電図検査、マスター負荷心電図検査
- ホルター心電図
対象疾患
- 虚血性心疾患(狭心症、急性心筋梗塞、陳旧性心筋梗塞、不安定狭心症、冠攣縮性狭心症)
心臓の血管が狭くなること(狭窄)により心臓の筋肉への血流が低下する、もしくは詰まって(閉塞)しまい、心臓の筋肉への血流が遮断される病気の総称を虚血性心疾患といいます。血管の狭窄により血流が低下した状態にとどまっている病気を「狭心症」といい、血管が完全に閉塞し、心臓の細胞が壊死した状態を「心筋梗塞」といいます。 - 心不全
心不全とは心臓のポンプ機能(全身に血液を送り出す機能)がうまく働かず、全身の血液の循環が滞ってしまう状態をいいます。心不全の症状はおおきく2つあります。一つは息切れ、呼吸困難など酸素不足によって起こる症状です。これは肺に血液がたまるうっ血によっておこります。もう一つはからだに水分が貯留するむくみです。心不全には急性心不全と慢性心不全があり、心不全を来す疾患としては、心筋梗塞、狭心症、拡張型心筋症、肥大型心筋症、心筋炎、弁膜症、先天性心疾患、心室頻拍、心房細動など様々です。 - 弁膜症 (大動脈弁狭窄症、大動脈弁閉鎖不全症、僧帽弁閉鎖不全症など)
心臓には効率よく血液を送り出すため、逆流防止弁が存在します。弁は、ポンプの働きをする左心室と右心室の、それぞれ入り口(僧房弁、三尖弁)と出口(大動脈弁、肺動脈弁) の計4ヶ所にあり、これらの弁が様々な原因で異常を来し、十分機能しなくなって起こる疾患を総称して「弁膜症」と呼びます。弁膜症は、弁の閉まりが悪くなって逆流を生じる「閉鎖不全症」と、弁の開きが制限されて流れにくくなる「狭窄症」との二つに分けられます。近年よく見られる弁膜症は、加齢とともに弁が硬化して起こる「大動脈弁狭窄」と組織の変性で弁が弛んでおこる「僧帽弁閉鎖不全」が主です。一般に弁膜症が重症になると疲れやすくなり、やがて息切れや呼吸困難などの心不全症状を自覚するようになります。病状が軽いうちは薬で対応できますが、症状が進むと手術が必要になります。 - 先天性心疾患 (心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、動脈管開存症など)
生まれつきの心臓の異常を先天性心疾患と呼びますが、生まれつきの心臓病でも、生まれてすぐに症状が現れるわけではありません。症状は病気の重さによって異なり、乳児のころに手術を受ける方から、老年期になって異常に気づかれる方もおられます。 - 静脈, 肺循環疾患 (深部静脈血栓症、肺塞栓症、肺高血圧症)
全身から戻ってきた血液を肺に送り届ける血管(肺動脈)に、血液のかたまり(血栓)が詰まった状態を「肺塞栓症」といいます。原因としては、下腿の静脈にできた血栓が心臓を介して肺に運ばれて起こることがほとんどで、長時間動かず同じ姿勢でいることで下腿の静脈の血流が滞り、血栓ができてしまいます(深部静脈血栓症)。一般的には、飛行機内のエコノミークラスのように狭くて動きづらい環境下で、長時間着席したままの状態でいることで生じることが多いため、エコノミークラス症候群とも呼ばれています。 - 不整脈(心房細動・粗動、洞不全症候群、房室ブロック、心室頻拍・心室細動)
不整脈疾患は心臓の病気のうちでも最も頻度の高いものであり、正常の心拍が保てなくなる状態をいいます。不整脈には大きく分けて2種類で、脈拍が早くなる頻脈性不整脈(目安:1分間に100回以上)と、遅くなる徐脈性不整脈(目安:1分間に50回以下)があります。 - 心筋、心膜疾患 (心筋症、心筋炎、心膜炎、心嚢液貯留)
心筋症は心臓の筋肉の病気で、心臓の筋肉(心筋)が障害され、その結果、全身に十分血液を送ることのできなくなる病気です。原因不明の場合を「心筋症(特発性心筋症)」と呼んでおり、心筋が異常に厚くなる「肥大型心筋症」、心臓の内腔が拡張して心筋が薄くなる「拡張型心筋症」、心筋が硬くなる「拘束型心筋症」の3つのタイプに分類されます。また、原因、全身疾患との関連がはっきりしているものを「二次性心筋症」、あるいは「特定心筋症」と呼んでいます。虚血性心疾患による「虚血性心筋症」、弁膜疾患による「弁膜症性心疾患」、高血圧による「高血圧性心疾患」は頻度の高いものです。アルコール多飲による「アルコール心筋症」、出産後の女性に起こる「産褥性心筋症」などもあります。
また、頻度は低いですが、「心サルコイドーシス」や「心ファブリー病」など診断をつければ治療可能な疾患もあります。 - 動脈疾患 (閉塞性動脈硬化症、大動脈炎症候群、その他末梢動脈疾患)
末梢の動脈(頸動脈や上下肢の動脈、腎動脈)に動脈硬化、炎症が原因で、狭窄、閉塞を来し、血流障害をおこす疾患です。 - 失神発作
数十秒程度の短い時間に、血圧が低下して心臓から脳に送る血液量が少なくなり、脳全体が酸素不足になって意識を失う発作です。意識を失うと立位を保持できず、患者さんは転倒して頭頚部などに受傷することがあります。
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|
| 入院患者 | 1,064 | 1,067 | 1,011 |
| 手術・検査名 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術(PCI) | 245 | 242 | 229 |
| 緊急PCI | 106 | 91 | 70 |
| ロータブレーター | 20 | 14 | 11 |
| diamondback | - | - | 14 |
| 経皮的心肺補助 (PCPS) |
3 | 7 (うちIMPELLA 4) | 9 (うちIMPELLA 7) |
| 心筋生検 | 2 | 3 | 4 |
| 心臓カテーテル検査 | 564 | 505 | 663 |
| EVT(LEAD/CLTI/ALI/腎動脈/鎖骨下動脈) | - | 92 (51/36/3/1/1) |
89 (45/36/1/4/3) |
| シャントPTA | - | 97 | 108 |
| 心エコー検査 | 6,718 | 6,539 | 6,832 |
| 経食道心エコー検査 | - | - | 157 |
| 頸動脈エコー検査 | 1,054 | 1,028 | 1,024 |
| トレッドミル運動負荷検査 | 186 | 177 | 150 |
| ホルター心電図 | 1,675 | 1,536 | 1,588 |
スタッフ紹介

| 氏名 | 中島 健爾 |
|---|---|
| 役職 | 副院長 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |

| 氏名 | 髙岡 秀幸 |
|---|---|
| 役職 | 愛仁会 理事長 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |
| 氏名 | 松寺 亮 |
|---|---|
| 役職 | 部長 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |
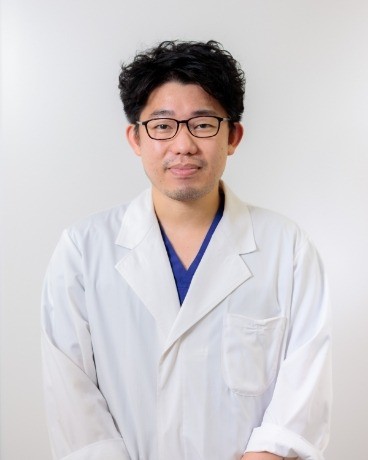
| 氏名 | 谷村 幸亮 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |

| 氏名 | 田中 悠介 |
|---|---|
| 役職 | 医長 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 |

| 氏名 | 上村 航也 |
|---|---|
| 役職 | 医員 |
| 資格 | 日本内科学会認定内科医 |
| 氏名 | 藤原 正貴 |
|---|---|
| 役職 | 専攻医 |
| 氏名 | 齋藤 勝太郎 |
|---|---|
| 役職 | 専攻医 |
| 氏名 | 篠原 祐樹 |
|---|---|
| 役職 | 専攻医 |
外来担当医表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 (初診以外は 完全予約制) |
中島 上村 |
谷村 | 髙岡 中島 |
神末 | 松寺 |
| 午後 (完全予約制) |
齋藤 | 田中(悠) | 篠原 | 藤原 |
・受付は11:00までとなります。
ACCESS交通案内
〒569-1192
大阪府高槻市古曽部町1丁目3番13号
交通案内情報を見る
- TEL072-681-3801
- FAX072-682-3834

電車でご来院の方
-
JR高槻駅徒歩9分、阪急高槻市駅徒歩15分
車でお越しの方
-
高槻病院西駐車場、
愛仁会リハビリテーション病院
地下第1駐車場がございます。