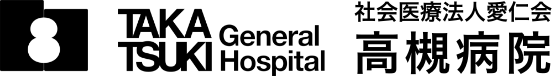メディカルナビ
肝炎ウイルスのほか生活習慣病も原因に 定期的な検査で肝臓がんの早期発見を
2025.02.17
当記事は地域情報誌「シティライフ」のニュースサイトからの転載です。
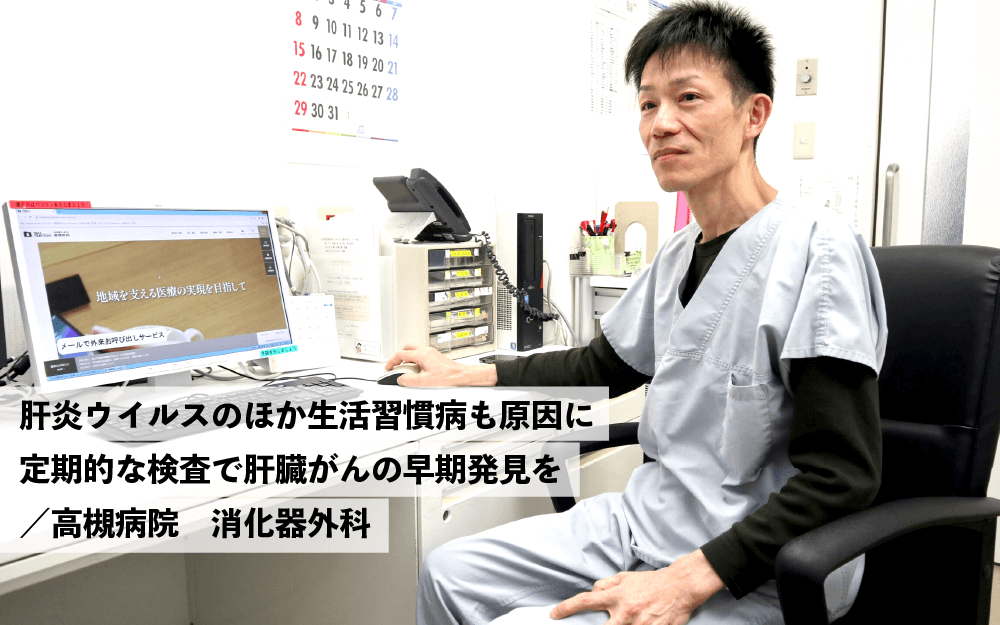
副院長・消化器外科 千堂 宏義
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、肝臓がんになってもほとんど気が付きません。症状が出た時にはかなり進行していることが多いです。「要因の一つである生活習慣病のある方は注意が必要です」と話すのは、高槻病院 副院長 消化器外科の千堂宏義医師。肝臓がんの要因や症状、日ごろ気を付けるべきことなどを伺った。
肝臓から発生する原発性肝がんには、肝細胞からできる肝細胞がんと肝臓内部の胆管からできる肝内胆管がん(胆管細胞がん)がある。その約9割は肝細胞がんで、慢性肝炎から肝硬変を経て、肝臓がんになることが多いです。どのような種類のがんであっても早期発見・早期治療が何よりも重要ですが、「沈黙の臓器」と呼ばれる肝臓は肝炎やがんになっても自覚症状のない人が多数。症状が出たころには重度になっている場合もあります。尿が濃い、目が黄色い、体がかゆい・だるいといった黄疸(おうだん)の症状は、肝臓が弱っているしるし。消化器内科を早めに受診しましょう。
肝臓がんにつながる慢性肝炎を引き起こしやすいのは主にB型、C型肝炎ウイルスの感染者。また、過剰飲酒はアルコール性肝炎につながることがあります。近年増加しているのが非アルコール性脂肪肝炎。脂質や糖質のとりすぎ、運動不足など生活習慣の乱れで肝臓に脂肪がたまるのが大きな要因と考えられています。肝臓の健康を保つにはまず、バランスのよい食事や運動などで生活習慣を整えましょう。肝炎ウイルスに感染していないかの確認も重要です。感染者はもちろん、糖尿病や脂質異常症といった生活習慣病を抱えている人は特に注意を。「健康診断でALT(肝臓の状態の指標)の値が高かった」など気になることがあれば、肝臓のエコー検査やCT検査を定期的に受けることをお勧めします。
高槻病院では消化器内科、消化器外科が連携して肝臓の検査や治療を行っています。肝臓がんと診断されたら、肝切除の手術のほかラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法、抗がん剤を使った化学療法などを病状に合わせて提案します。症状が分かりにくい肝臓だからこそ、体調で気になるところがあれば積極的に受診するようにしましょう。
 3Dシステムを使用した内視鏡外科手術の様子 3Dシステムを使用した内視鏡外科手術の様子 |
|
日本肝胆膵外科学会名誉指導医。高難度の手術を多数執刀し、生体肝移植にも携わる。 |