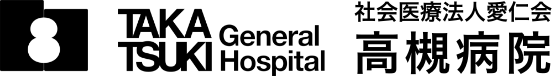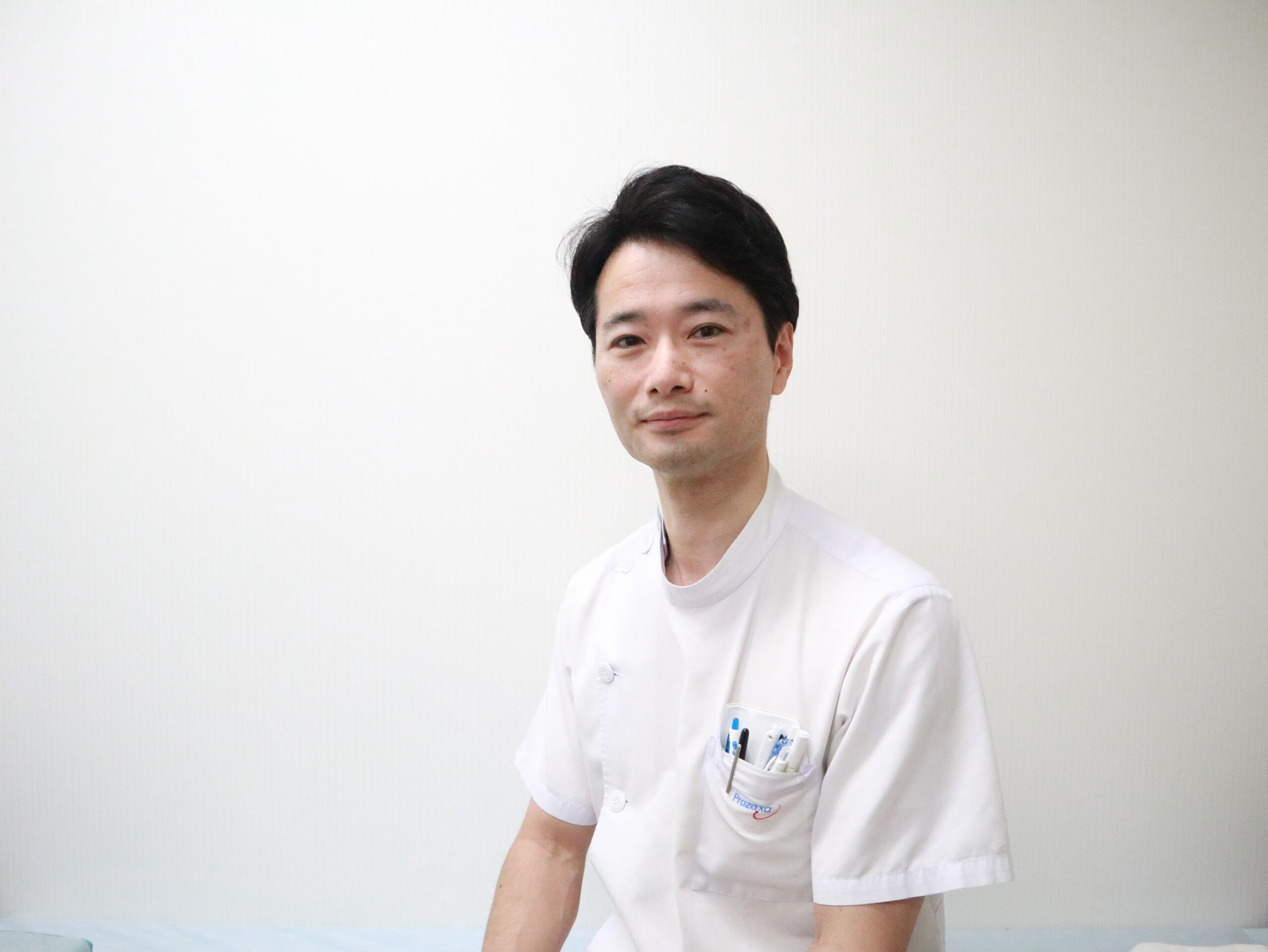メディカルナビ
突然の息切れやむくみは要注意 「年齢のせい」ではなく心不全かも
2025.07.18
当記事は地域情報誌「シティライフ」のニュースサイトからの転載です。
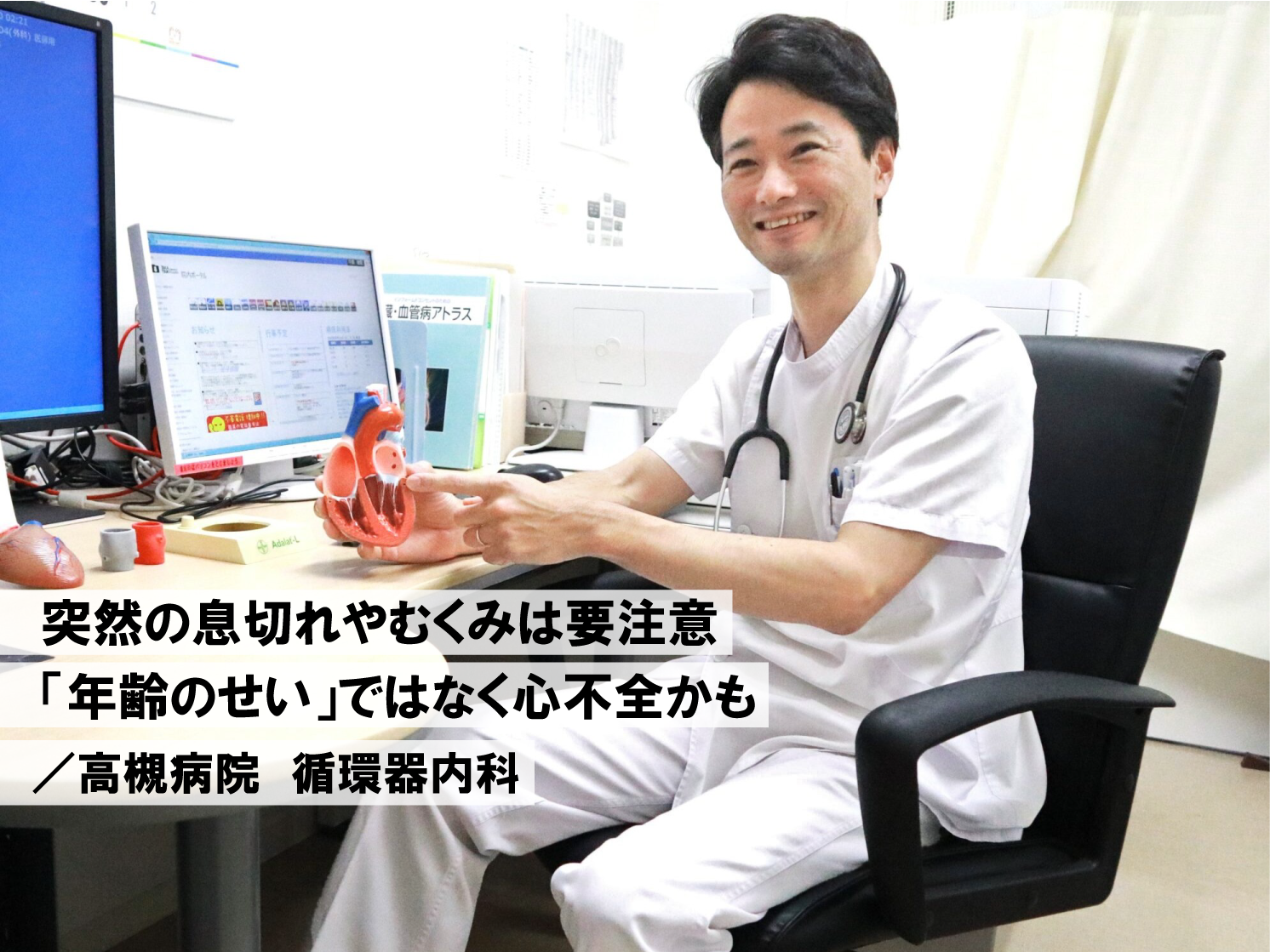
高槻病院 副院長/循環器内科 主任部長 中島 健爾
「心不全」とは、心臓のポンプ機能が低下して体内の血液循環が滞っている状態。罹患者は75歳以上が多く、進行すると安静時でも動悸・息切れが起こり、日常生活が制限されることも。原因となる他の心疾患や、日常で取り組みたい予防策について、高槻病院循環器内科主任部長の中島健爾先生に聞きました。
「動くと息切れする」「足がむくむ」「夜に何度もトイレに起きる」。高齢者にありがちな症状ですが、実は心不全のサインと共通しています。心不全とは、心臓のポンプ機能が低下している状態。血液を押し出す力が弱まると全身に血液が行き渡らず、けん怠感や手足の冷え、動悸などの症状が現れます。また、血液を取り込む力が低下すると各部で血流が停滞。下半身のほか肺や腸にも水がたまり、むくみや息苦しさ、咳、食欲不振などがみられるように。また、夜に横になることで腎臓の血流が回復し、たまっていた水分を排出しようとして夜間頻尿になることもあります。
初期のステージでは、「坂道を上ると息が切れる」など動作を行うことで症状が出ますが、進行すると立っていられないほど息苦しくなったり、呼吸困難で救急搬送されたりという患者さんもいます。息苦しいから、と動かないでいると要介護予備軍の「フレイル」状態に陥ってしまう危険性も。息切れや疲労感、食欲不振などを「年だから仕方ない」と放っておかず、気になる症状があれば早めに治療を行うことが大切です。

心不全の背景には、他の心臓の疾患が隠れていることがほとんど。狭心症や心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈などにより心臓の働きが弱ってしまうのです。さらにこれらの心疾患の原因をたどると、高血圧や高脂血症、脂質異常症といった生活習慣病ということになります。生活習慣病はすでに心不全のステージA。まずは日頃から「塩分控えめの健康的な食生活」「禁煙」「適度な運動」を心がけることが、心不全の予防につながると考えましょう。健康診断で心電図や血圧の値をチェックすることはもちろん、習慣として血圧や体重を測る、検脈をするのもおすすめです。
心不全の場合は心臓の血管が弱っている可能性があるので、冬場のお風呂など気温差に気を付け、排便時のいきみなど血圧が上がる行為は避けましょう。
診察においては足のむくみの確認や聴診を行うほか、胸部レントゲン、心電図、エコーなどを使用。肺に水がたまっていないか、心臓の弁の逆流はないかなどを確認します。心疾患によっては手術を行う場合もありますが、心不全の治療のベースは内服薬。近年ではより効果の高い新薬が開発され、きちんと内服すれば軽度の場合は支障なく日常生活を送ることができます。「急に息切れがひどくなった」など異常を感じたら、早めに受診してください。
|
日本内科学会認定内科医 総合内科専門医、日本循環器学会専門医。患者の不安を取り除けるよう、わかりやすい説明をモットーとしている。 |