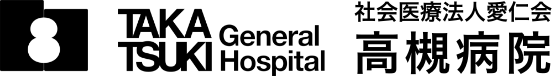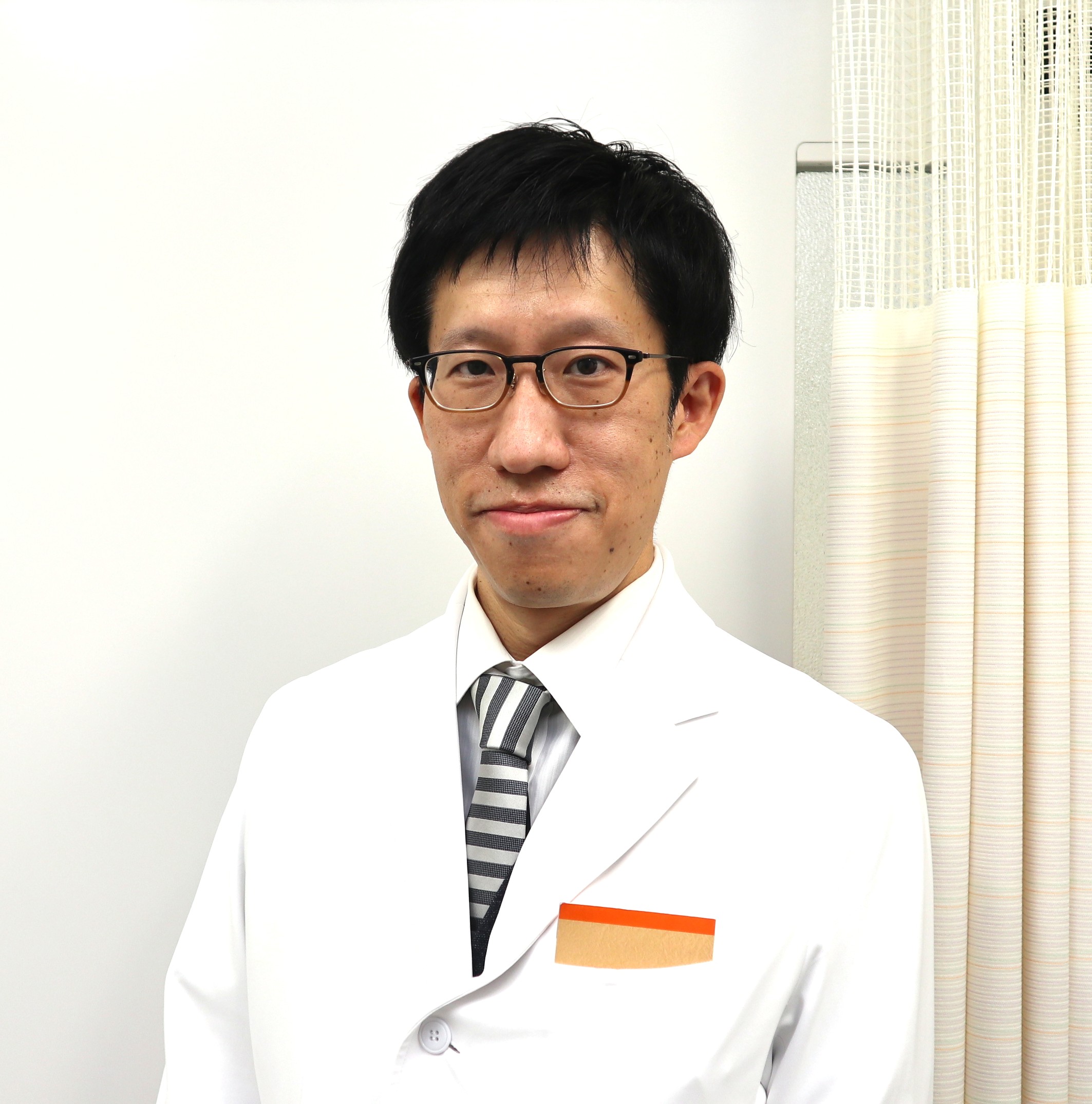メディカルナビ
専門外来で認知症を幅広く診療 アルツハイマー病の新しい治療薬も
2025.05.08
当記事は地域情報誌「シティライフ」のニュースサイトからの転載です。
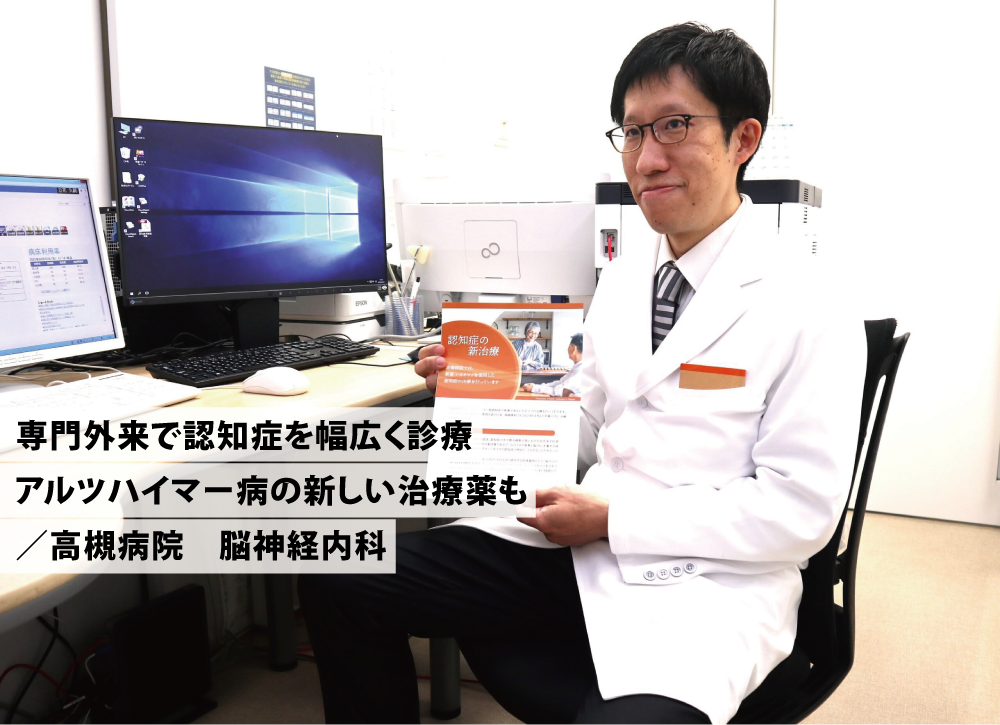
脳神経内科 医長 立花 久嗣
高齢者人口がピークを迎える2040年には、認知症患者が約584万人、65歳以上のおよそ7人に1人が認知症患者になるという推計を厚生労働省の研究チームが発表しました。誰もがなりうる病気であり、多くの人にとって身近な「認知症」について、その症状や治療法、新しく国内で承認された治療薬について、高槻病院で「認知症外来」を担当する、脳神経内科医長・立花久嗣先生にお話を伺いました。
「認知症」とは、もの忘れ(認知機能障害)などの認知機能の低下によって日常生活に支障をきたす状態です。代表的な病気はアルツハイマー病で、65歳以降の高齢者の方に多く発症し、「昨日何をしたか」といった最近体験したことの記憶(エピソード記憶)が抜け落ちてしまうのが一つの特徴です。
初期には、「今まで使えていた電化製品が使えなくなった」、「億劫になり、やる気がでない」などの症状がみられます。ご本人には自覚がない場合もあるので、ご家族や周りの方が違和感に気付いたら、早めに認知症(もの忘れ)外来や脳神経内科の受診を勧めましょう。早期から生活改善などの治療をスタートすることで、症状の進行を抑えられる可能性があります。
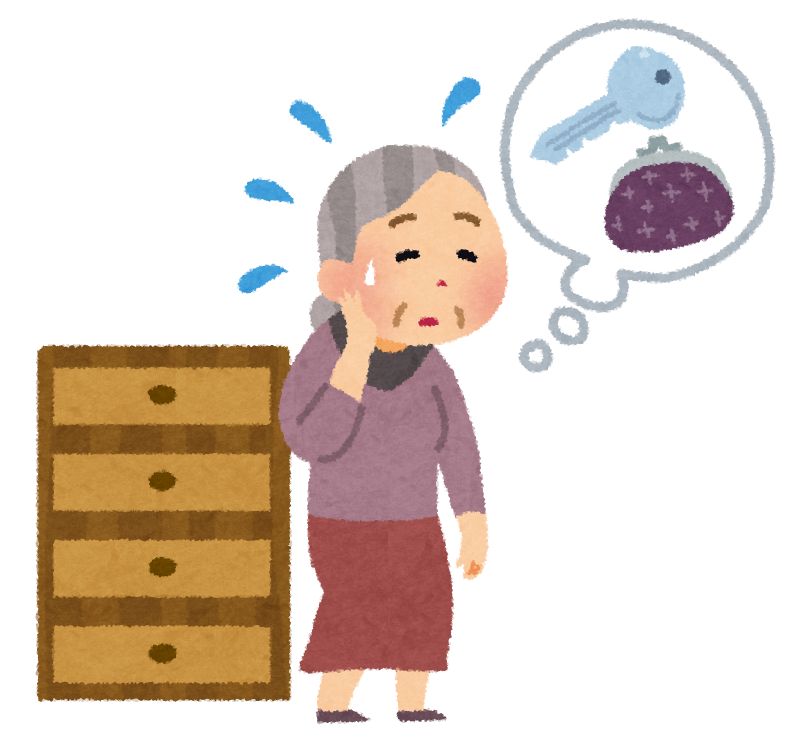
認知症にはアルツハイマー病以外にも病気があるため『認知症外来』ではもの忘れの原因が何か考えることから始まり診断により治療の方向性、薬物療法の適格性について説明します。『精神科』と連携してイライラ、不安、抑うつといった認知症の周辺症状に対して薬物治療を行うこともあります。もの忘れが軽度なため薬物療法の対象ではない方は『認知症予防・初期もの忘れ外来』にて生活指導、運動指導などを受けていただくこともあり、当院ではもの忘れの病期によってさまざまなアプローチが可能です。
近年、アルツハイマー病の原因の一つとされる脳内のタンパク質「アミロイドβ」を除去することで、認知症の進行を遅らす効果が期待できる薬「レカネマブ」「ドナネマブ」が新たに国内で承認されました。2週間に1回通院し(「ドナネマブ」は、4週間に1回通院)、一定期間点滴で投薬を行なう治療で、当院では、「レカネマブ」「ドナネマブ」の新薬による治療も導入しています。従来の薬とは違い、認知症と診断された患者様だけでなく、軽度認知障害(MCI)の方も対象となりますが、投薬にあたっては、問診やMRIなどで精密な検査と診断を行ない、医師との相談の上で治療を進める必要があります。認知症の症状や進行スピードは、人によってさまざまです。患者様一人一人に寄り添った治療プランを提案させていただきます。
|
脳神経内科医。日本認知症学会専門医。東京慈恵会医科大学卒業後、兵庫県立尼崎病院勤務、神戸大学医学部付属病院助教などを経て、高槻病院脳神経内科で勤務。 |